3月26日(日)
訃報にともなって湧き出した大江健三郎の話題をアレコレ読みながら、ほとんど関係ないが『ゆきゆきて、神軍』を思い出した。神軍平等兵、奥崎謙三を追った原一男監督のドキュメンタリー映画。奥崎氏の著書に、『奥崎謙三服役囚考 あいまいでない、宇宙の私』(新泉社)というタイトルがある。97年7月刊行。これは97年1月に刊行された大江健三郎の講演録『あいまいな日本の私』(岩波新書)をもじっている。と、そんな連想から『ゆきゆきて、神軍』の記憶にスポットライトが当たり、夕飯をつくり食べしつつ片手間に流し観たのだった。
ところで、わたしの頭の中では上記のような脈絡を逸した連想がしばしば働く。こうした傾向から、さらに連想したのは再読していたラルフ・ジェームズ・サヴァリーズの『嗅ぐ文学、動く言葉、感じる読書 自閉症者と小説を読む』(みすず書房)だった。著名な自閉症者であるテンプル・グランディンのこんな話が引かれている。
たとえば、オリンピックのフィギュアスケートについて書かれた『タイム』誌の記事にこのような文章がある。「すべての要素が整っている――スポットライト、湧き上がるワルツやジャズの調べ、そしてスパンコールを身にまとい宙を舞う妖精たち」。テンプルは、この文章を読むと、「頭の中にスケートリンクとスケーターが思い浮かぶ。けれども『要素(エレメント)』という言葉をじっと考えていると、学校の化学教室の壁に貼ってあった元素(エレメント)の周期表という、この場面にそぐわない連想が生じる。『妖精(スプライト)』という言葉で立ち止まると、可憐な若いスケーターではなく、冷蔵庫の中の『スプライト』の缶のイメージが浮かんでくる」と言うのである。彼女自身は自分のこうした連想的性向を学習の妨げと見ていた。p.249
しかし、文芸作品の創作においてはむしろ強みやんけコラァ! とサヴァリーズ氏はこのあとにつづける。「やんけコラァ!」はわたしの創作だが、そのぐらいの勢いを感じた。「冷蔵庫を開けたらスプライトが二回転のトゥループジャンプを跳んで床に着地した。泡とスパンコールの乱舞だ!」(pp.249-250)とかなんとか書いてある。こっちはサヴァ氏の創作。
たしかに、比喩や掛詞などの方法を駆使して意味を重層化するにはうってつけの思考回路かもしれない。文学のなかでもとくに詩歌と親和的だろう。小説的でもある。もちろん連想のドライブに乗っていく傾向がすなわち自閉症的とはかぎらない。たぶん、程度による。すこしだけ、わたしの思考の進み行きもテンプルと似たところがある。道草を食いながら蛇行する。そのような整序されない表現過程にリアリティをおぼえもする。記憶がじかに声を発しているような。そこらじゅうから共鳴していく。ひとりの人のなかで育まれた想起のネットワークが縦横無尽に広がりゆく感じ。
マドレーヌを紅茶に浸したそのとき、過去の記憶がよみがえる。『失われた時を求めて』の有名なくだりは、「脈絡を逸した連想」の好例だろう。ごくふつうに考えれば、単に「おいしいね、もぐもぐ」で終わりそうなところ。なんで過去に飛ぶのかわからない。しかし、小説の人物が語る固有の記憶のなかでは紅茶とマドレーヌが過去への入り口になりうる。とても自然に。
そういえば、そういえば、そういえば……と、記憶はいつも泡のように湧いては消える。本筋はどこにあるのか、一向に見えてこない。それでよいのかもしれないと、このごろは力なく思う。なんのために生まれて、なにをして生きるのか。写真を撮ることも、文章を書くことも、本を読むことも、映画を観ることも、音楽を聴くことも、あまり自分の人生には関係がない気がする。中身のない気泡をポコポコ湧出させるようにしてフワフワ生きている。泡沫の日々。筋をつけるには、力がいる。すべてにさらされるばかりで、まとまらない。把持できないまま時間が流れる。それでよいのかもしれないと、このごろは力なく思う。
記憶は、けんけん遊びのようなもので、ぴょんと跳ね、立ち止まり、またぴょんと跳ねる。
すると、Mが言う、周縁的なものが非連続を成すのなら、主筋は連続性を形成するのだと。
でもここは慎重にいこう――何が主筋で、何が副筋云々であると、誰がわたしに言うのか。これら数々の糸、様々なつながり、閉じられぬ終わり、偶然が描く文様。
跳んでごらん、さああなたも、ぴょんと。飛び越してごらん。
イルマ・ラクーザ『もっと、海を ――想起のパサージュ』(鳥影社、p.389)より。ぴょんと。それでいえば、奥崎謙三は生涯を通じて主筋をつらぬいた人物ではなかったか。彼に副筋はない。奥崎謙三は他の誰でもなく、奥崎謙三でありつづけた。うつろいやすい人間の法より、変化しない神の法を信じていた。映画のなかでは、戦争の記憶を執拗に問い詰めた。戦中との連続性を追及する奥崎と、不連続にのらりくらりと戦後を生きる人々の対照が印象的だった。言い換えれば、静止した時間と経過した時間との対照。
奥崎謙三は静止した時間を体現している。存在がトラウマそのもの、というか。穏やかな戦後の時空間を喰い破り、関わる人をことごとく戦中の時空間へ連れ戻そうとする。映画の観客もろとも。それぐらい強力な磁場を感じた。「ぴょん」というような軽みがまったくない。話が飛ばない。頑として、ひとりの、ひとつの時間を生き続けたのだと思う。あるいは、どこかの時点からそうせざるを得なくなったのか。つねに切迫的で、切実な怖さがあった。
これは『ゆきゆきて、神軍』のひとコマを加工したもの。
なんとなく、「写真に撮りたい場面」をうかがいながら映画を観ている。やはり、凡庸だけれど、感情的に盛り上がる部分は撮りたくなる。人が暴れているところとか、落ち込んでいるところとか。喜んでいるところは見過ごしがちか。ポジティブより、ネガティブを撮る傾向はある。撮りたくなるのは、「不穏さ」。
これはウニー・ルコント監督の『冬の小鳥』。
この映画も静止した時間、つまりトラウマを描いたものだった。孤児院に入れられた少女の時間。監督自身の体験を踏まえてつくった作品だそう。ウニー・ルコントはインタヴューでこんなことを語る。
実際、私はこの映画を撮っても100%乗り越えることができていない。トラウマの体験ってそういうものだと思うの。トラウマだからね。常に不安に襲われ、いつでもそうなる可能性がある。それが繰り返すの。それがこの映画のストーリーよ。彼女は父親との別離を一度は乗り越えるけど、それはもう一人の少女、スキと友達になれたから。でもすぐにまた次の別れが訪れる。2人とも別々に養子縁組されてしまうから。それが私たちの人生の物語よ。一緒になっては別れる…。そこには長いプロセスがあるの。乗り越えても倒れ、また立ち上がる…。だから一度映画を作ったからと言って、乗り越えたと、過ぎたことにするのはむずかしいし、そうなるとは決して言えないわね(笑)。
OUTSIDE IN TOKYO / ウニー・ルコント『冬の小鳥』インタヴュー
「過ぎたことにするのはむずかしい」、そんな静止した時間は誰のなかにもあると思う。大なり小なり。その終わらない感情が作品になる。奥崎謙三にとっての「神」とは、きっと彼の「終わらない感情」を指している。ルコント監督にとっての「終わらない感情」は、孤児院で過ごしたひとときのなかにあった。強い感情の経験は、ひとつのパターン、ひとつのリズムとして体に刻まれ、人生のなかで何度も繰り返される。ここで語られている「トラウマ」は、「感情の原型」とも解釈できる。原感情みたいなものについて話をしている。
「ペレジバーニエ」というロシア語を思い出す。ユーリ・ノルシュテインがよく語っている。ルコントの「トラウマ」もたぶん、その話だ。「追体験」や「追憶」を意味する。「情動をともなう心理的困難を生き抜く」、といったニュアンスがあるらしい。ある論文のなかでは、「情動体験」と訳されていた。ノルシュテインは赤子が泣くようすを例に挙げてペレジバーニエを説明する。それは「絶えず、呼び起こさなくてはいけない」のだと。生きるための、いちばん最初の感情のこと。
トラウマは一般に、「呼び起こしてはいけない」というニュアンスで語られる。意味は近いけれど、扱いが真逆だ。思うに、トラウマとペレジバーニエの関係は、PTSD(心的外傷後ストレス障害)とPTG(心的外傷後成長)の関係に近い。どちらも外傷が起点。でも、経過が異なる。とはいえパキッと分けられるものではなく、「障害」と「成長」は行きつ戻りつ揺動する。物語を紡ぐように。そして、これらのあいだを右往左往する話が郡司ペギオ幸夫の『やってくる』なのだと思う。
“だから「やってくる」人というのは、常日頃、例えば、シニフィアンとシニフィエのアンチノミー――そのアンチノミーというのはわかりやすいものではなく肯定的アンチノミーでありながら否定的アンチノミーであるようなもの――を抱え込んでいる人だと思います。同じ悲惨な体験をしても、PTSDになる人というのは10%ぐらいらしいですが、トラウマを持つ人は、芸術家ともなり得る感度のいい人だと思いますから、少数派と言っても、このような人たちをないがしろにする社会は、変革や創造の力を失うと思います。むしろ、広い意味でのトラウマを抱え込んで磨く、ということが、「やってくる」エンジンだと思います。”
【イベントレポート】郡司ペギオ幸夫×宮台真司トークイベント「ダサカッコワルイ世界へ」文字起こし④ | 特集・記事 | 代官山T-SITE |
抱え込んで磨く、呼び起こせるトラウマ。郡司氏の言う、「やってくる」エンジン。それは、ノルシュテインのことばで言えば「ペレジバーニエ」なのだ。なるほど「やってくる」と「ペレジバーニエ」は響き合うのか。と、なんかわかったような気がしたが、じゃあ「ペレジバーニエ」とはそもそもなんなのか。新たな言い換えを発見しただけだ。でも、言い換えというのは重要で、そうやって、すこしずつ外堀を埋めていく。書くことは不断の言い換えであり、それ以上のものではない。わたしはいつも同じところをぐるぐるしている。同じ人が書いているのだから仕方がないか……。

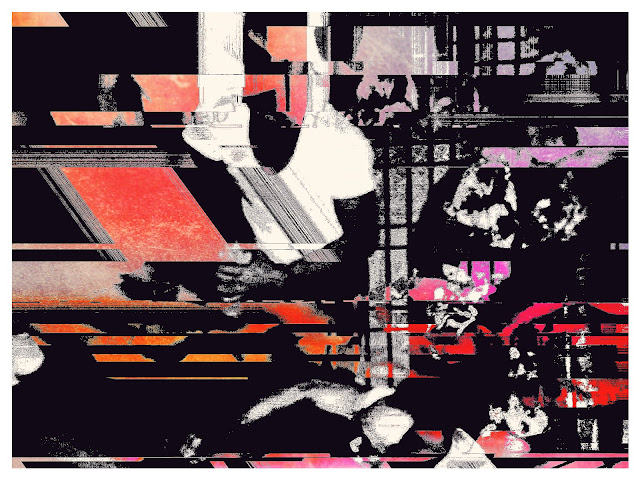

コメント